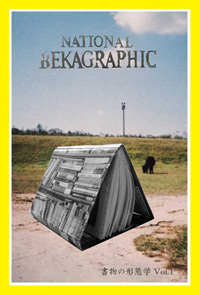「身体としての書物」
第1回
アルドゥスに倣びてー八折り本を作る
第2回
ボルヘス「砂の本」を読む
第3回
ボルヘス「バベルの図書館」を読む
第4回
ボルヘスと焚書について
特別篇
川べりの本小屋で ー山口昌男氏との対話
第5回
「ボルヘス・オラル」を読む
第6回
ジャベス「書物への回帰」を読む
第7回
ジャベス「問いの書」を読む
第8回
ページネーション考 1
第9回
ページネーション考 2
|
|
「身体としての書物」 今福龍太
特別篇 川べりの本小屋で ー山口昌男氏との対話 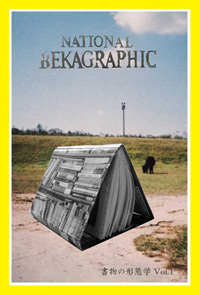
今福 山口先生とすこしあらたまったかたちで対話をする機会はこれまで何度かあったのですが、そんなとき、ぼくらはつねに何冊かの本をかたわらに置いて、ある特定の本とそれがつくりだす風景のことをもっぱら話題にしてきた、と言っていいでしょう。ですが今回は、山口先生とただ「本」について語りたい、個別のタイトルや内容をもった本ではなく、本そのものついて純粋に語りたい、と、そう思っています。
今日のトークの小さな会場である、このギャラリー・マキの空間の入り口から、すでに府中の山口文庫の書棚を撮影した写真が、文庫そのものの混沌として雑然とした感触を残すようにして立体的に展示=再現されています。ですから先生にしてみれば、府中の自宅から隅田川沿いのギャラリーにふらっと来てみたら、またぐるりと文庫の宇宙にもどってしまった、そういう感覚かもしれませんね。
さて、ぼくの山口先生との交流はもう30年近くになりますが、これまでアメリカやメキシコ、日本でもさまざまな土地でお会いして、先生の本漁りのあとを追いかけながら、何かを学びつづけてきたようなところもあります。そういうとき先生は、都会の新刊書店や古書店だけではなくて、かならず(注:ここの展示にもあるような、と背後の簡素なブックスタンドを指さして)キューバの路上でみかけるような露店の古本市などに立ち寄ってゆく。そしてそういう精力的な本漁りの現場に接するたびに、山口昌男という身体と頭脳が、本の神話的世界へ入ってゆくときの驚異的な連続性の感覚、書物ととりむすぶ多様なコミュニケーションのありようというものに、いつも深々とした衝撃を受けてきました。今日は、山口先生との対話を通じて、そうした本のある神話的風景について話せることができれば、と思っています。
ぼくらの目の前にゴロンと置かれた丸太の根元に、ちょっとした遊び心で、こうして二冊の本を並べておきました。一冊はブレーズ・サンドラールの『黒人詞華集』、1927年に出版されたものです。ここにあるぼくが編集した『山口昌男著作集』の「知」と題された第一巻に、山口昌男とサンドラールが共有する本質的なアンソロジー感覚について解説を書いておきましたけれども、27年に出版されているということで、ほぼ山口先生と同じ時間を生きてきた本、山口昌男の生命の時間そのものを体現する象徴的な本としてもってきたわけです。これぐらいの時間を生きるとページの端の紙もぼろぼろ粉になって崩れ落ちたりして、つまりいろいろな意味で年輪のきざまれた書物ですね。人間の方も同じですが・・・(笑)。
それからもう一冊が、クロード・レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』。これはパリのプロン社から「人間の大地叢書」という、ヴィクトル・セガレンの『記憶なき民』とかジャン・マロリーの『トゥーレの最後の王』とかいった地誌・人類誌の傑作がならぶシリーズの一冊として1955年に出されたものです。折り丁にナイフを入れて読むタイプのペーパーバックですね。そしてぼくとまったく同年齢で、紙の黄ばみはサンドラールほどではないですが、でもご覧のとおり、本じたいとしては少しくたびれてきている(笑)。
山口 レヴィ=ストロースのこれはね、刊行されてしばらくして丸善で手に取ったけれども、当時4、5000円ぐらいだったかな、ちょっと高いなと思って棚にもどした記憶がある。
今福 ああ、そうでしたか。そういう私たち二人の個人史的・生物学的な時間と、書物の年齢というふたつの時間がここにならびたっていて、それは同じ時間を物理的に刻んできたものである--そんな暗示をこの場所にあたえてから、さっそく先生におはなししていただきたいのですけれど、まず、いま「情報」といった概念やテクスト至上主義に本が囲い込まれているような現状があるわけですが、そういう本ではない、モノとしての書物が、先生にとってどういう存在だったかを、まずお聞きしてみたいと思います。
山口 本が人間にとってどういう「かたち」であらわれるのかという問いかけが今福先生のほうから出ましたが、まず字そのもの、書かれた文字がコレクションの対象となるようなカリグラフィーというものがひとつある。それから、ホメロスの詩歌の場合のように、背後にイメージの風景を想像させる建物としての本、というものも考えられるであろう。それからオーストラリアの先住民や、西アフリカ・サハラ砂漠の部族の描く、旧石器的な洞窟壁画のような絵もそういうものであるし、古代・中世の日本には絵巻物などがあったわけです。現代のアジアや南アメリカなどでは、権力闘争のなかでメディアとして非常に弱いものをとおして抵抗を訴える、それがモノとしての本でもありうる。と、こうした時空の遠近の離れなかで、本の「あらわれ」は多様なものであったと言えるわけです。
私個人にとっての本の原風景というのは、夢中になってむさぼり読んだ「少年倶楽部」などのマンガ雑誌でしたね。これはいまや古典文献なりつつありますが、少年時代、小中高をつうじてひそかに図書館にこもり、分厚い雑記帳にひたすらマンガを描いていた、そうやってたったひとりで書物を作っていた、と言ってもよかろうと思います。
今日は、水野成夫についてちょっと話そうと思ってきたのですが、この人物は戦前から文学や芸術に対する非常に深い知的好奇心を持っていまして、そこからマルクス主義に接近してゆく。3・15事件で逮捕されて獄中で転向したりして、それから共産党批判を展開するのですが、政治活動家としてはこの時期に挫折して、アナトール・フランスなどの小説、たとえば『ペンギンの島』であるとか『天使の反逆』といった作品の翻訳をはじめるわけです。大正時代におけるアナトール・フランスの翻訳作品というのは、『白き石の上にて』に代表されるように、ユマニスムから見た同時代史を体現している。ともかく、水野は書物を媒介にして世界そのものをみずからのもとに呼びこんでいたところがあります。それから財界に進出して海軍の協力を取りつけて、日本製紙(大日本再生製紙)をたちあげるなど、紙とのつながりをもっていた。そういうところから戦後はさらにマスコミのほうにも乗り込んで、産經新聞の社主になった。フジサンケイグループは、上野の森美術館とか彫刻の森美術館を擁していますが、こうした懐の深さというのは、水野成夫によるところが大きい。水野は経営者でありながら芸術の全体性をおさえて時代の隠された層を地下から掘り当てる才覚に秀でていたわけです。ところがそうした挑発性ゆえに時代の反発も喰らって、出版ジャーナリズムや放送の世界から追放されるわけですね。
いまフジをバックに中曽根康弘などが顧問になって、世界文化賞なるイベントが今でも年に一回ひらかれているようですが、そうした現在の政治とジャーナリズムがいうところの「世界」は、所詮は水野的な世界の根源性を悪魔祓いして矮小化したうえでなりたつものである、という構図がじつは見えるわけです。ところで水野と言えば、後に野球経営にも乗り出して、現在のヤクルトスワローズ、神宮球場を本拠地にするのですが、このあいだ神宮外苑を歩いていたら、聖徳記念絵画館という西洋分の建築がありました。それまで私も知らなかったのですが、そこに『敗者の精神史』で書いた、やはりスポーツにおける身体的な知を介して同時代的な自由のネットワークを拡大していった仕掛人である小杉放庵の絵、「帝国議会会院式臨御」という作品が所蔵されている。こういう刺戟的な出会いを今に至るまで可能にするトポスを潜在的に隠し持つ明治神宮の問題とね、そこの造営にまつわる風水論的な思考という話題があるわけですが・・・(注‥ここで、ふさ子夫人により、「お父さん、今日は「風水」じゃなくて「本」のことを話しにきたのよ!」と間の手が入る)・・・えーと、これをやるには、あと一時間あっても足りない(笑)。
今福 今日は先生のはなしをさえぎらずに、ずーっと聞いてみたいという欲望もあるのですが(笑)。いま山口先生の自宅をたずねると、ちょうどの目の高さのところの棚に、水野成夫関係の本が並んでいるんですね。「身体としての書物」というぼくの授業のゼミ生だった野村さん、兼田さん、大山さんが共同で作った、この小冊子の背表紙の部分に、偶然その『人間 水野成夫』という本を撮影した映像がかさなって、それがある意味でこの冊子の潜在的なタイトルになっている。かれら学生にいわせると、この冊子は写真の向きとは天地が逆で、だからこそ、この冊子は『人間 水野成夫』ではありえないもう一冊の別の本だということにもなるのでしょうが、おもしろいですね。
さきほど先生が話されたのは、おそらく、たとえばこの『人間 水野成夫』という本から透視された世界と精神史の全体性ですね。紙と政治との関係など、書物論的にいっても非常に刺戟的な話題も出ました。ともかく、先生は一冊の本が何ものであるか、その可能性を無限に押し広げていこうとする。それは、ここにある『本の神話学』という先生の著書の語り口そのものなのです。たとえばフロイトなら、フロイトがどういう人物で何をやった人物であるかなどという情報はいっさい語らず、いきなり先生自身が面白いと思うフロイトの思想の核心にはいりこむ。そしてそのすべてを語り終える前に、いつのまにか語りは別の本、次なる意図へと移行して、けっして前にはもどらない、そういう語りのスタイルですね。だからこそ、こうやって螺旋状に展開する語りは、つねにその先に何があるのか、何と出会うのかがまるで分からないような仕掛けになっている。今日、なるべく口を挟まずに先生の話をじっと聞いたていたのも、語りの先にある未知なるものが一体何なのか知りたい、という好奇心がぼくのなかにつよくあるからで、一度ぐらい先生の語りを口を挟まず五時間ぐらい聞いてみたいような気もします(笑)。しかし、『本の神話学』の語りは、たんなる連想や思いつきで前進していくようなものでもなくて、書物と書物がおりなす網で世界の全体性を一挙にすくいあげる、そういうものです。先生が一冊の本を語ることが、つねに文庫の宇宙を語ることにもまっすぐ繋がるという意味では、文庫そのものがその大きな網なのかもしれません。山口文庫の本の並べ方というのは、まあ、基本的に統一的なルールがない、すくなくとも図書館や書店の分類ではつなげられない。そういう意味で非論理的なのですが、かといってメチャクチャに並べられているわけではないですね。先生にしか予感されえない、ある種の核心によってすべてが結ばれていて、それが大きな、書物の神話的な網の目を織りあげているのです。
ところで最近、寿岳文章という、先生もよくご存知の、書誌学者・英文学者で柳宗悦の民芸運動の同時代人、非常に意欲的なすぐれた個人書肆をたちあげたりもした人物で、いまや忘れられた存在であると言ってもいいと思いますが、その寿岳文章による、イデアとしての本、モノとしての本をめぐる驚くべき統合性をもった思想を再発見しつつあります。かれは戦後すぐ出た著書『書物の世界』において、書物をめぐって現時点においてもじつに刺戟的な発言をしているのですが、たとえば、「グーテンベルク版の聖書が、この世界に250部すべて残されていたら、書物の歴史は面白くない」ということを書いています。書物は損なわれ、やがて消えるものだという認識ですね。そこで『書物の敵』--19世紀の印刷工から書誌学者になった、こちらもいまや忘れられた存在であるウィリアム・ブレイズの著作からの引用という形で、本の10の敵を列挙しています。まず、1、火。これは、ある意味で最大の敵でしょうが、単純に火事で燃えるということだけではなくて、「焚書」の問題もここにあります。2、水。3、ガス。当時の図書館は室内にもガス灯を利用していて、これがしばしば爆発して火災の原因になったそうです。4、塵。かつては本の小口部分や天地に金箔を張ってあるものがありましたが、あれは、一般にそう思われているように豪華本の装飾ではなく、刷毛かなんかでさっと塵やほこりを払うことができるという実用的な処置ですね。5、無知と頑迷。これはやや抽象的な敵ですね。6、しみ。7、その他の害虫。8、製本士。当時の本はすべて仮とじ本で、個人が製本屋にいって装幀してもらっていました。本の形状やレイアウトなどの問題を無視して、小口をバッサリ切る、そういうことにブレイズは憤慨しているのです。そして、ここからが面白いのですが、9、蒐集家(笑)。玩物喪志のマニアックな書痴はいつの時代もいます。最後に10、下女と子供。下女は、本にはたきをかけて片付けるようでいてかえって文庫の内在的秩序を混乱させ、子供はいうまでもなく、本を投げたり蹴飛ばしたりする敵ということですね。
ここで、本は消滅するものである、という主題についてすこし話しておきたいと思います。山口文庫の居間の机には、コンビニで買ったマンガと、日本近代史の資料や掛け軸、それからブレーズ・サンドラールのフランス語詩集などが、たとえば何気なく並んでいます。本と本のあいだにまったく差別がない、ある種の本を特権化する態度がまったくなくて、これはぼくなどにはまだまだ到達できない境地ですね。この「分け隔てのなさ」、それこそがじつは山口昌男の本の思想の核心なのでしょう。そして山口文庫の自由な空気は、どこかで本が消えることを平然と受け入れている気がするんです。本が盗られたり、傷つけられたりって、これは通常のごく一般的な愛書家なら目くじらを立てる行為ですよね。
ここで憶い出されるのは、先生とも交流が深かったオクタビオ・パスが、亡くなる三年前に自宅が火災事故にあって蔵書のほとんどを失ったことです。パスが亡くなったあとに色々な人の追悼の発言をみていたのですが、多くの人が、この火事がパスの死を招いた、というふうに語っていたのが印象的でした。書物の焼失とともにあきらかにパスの精気が消えた、と口を揃えて言うのです。パスにとっての書物とは、何か経済的な価値に換言できる財産などといったものではなくてまさに身体の一部で、火災とはそれが奪われるという経験だったのでしょう。実際にこの事故の直後に病に倒れて入院し、それが結局死につながったわけですね。先生は、パスの自宅の蔵書をご覧になったと思うのですが・・・。
山口 いや、パスの自宅を訪ねたことはあるけれども、蔵書というのはみたことがなかったね。むしろパスとのあいだにはいつも絵があって、コバルビアスの作品とかを表のショーウィンドーに飾ってある画廊なんかをめぐって一緒に歩き回りながらはなした、という感じ。
今福 そうでしたか。ともかく山口先生にとっての本は、しかしやはりパスのそれとはちょっとちがうように思うんです(注:山口先生、深くうなずく)。先生はそれこそ本も活字もまったくないアフリカやインドネシアのフィールドに出ることもできて、つねにどこかで本を突き放しているようにも見える。ところが先生が先ほど話されたように、先生自身にとっての本の原風景は、雑記帳に自分で書いたマンガだった--スケッチブックも「ブック」という以上、本の一種なのかもしれませんが、スケッチブックだけは、きょうももってきていただきましたが、どこにいくにもかならずもっていって、フィールドの景観の背後にある世界像を絵やスケッチを描くことで読みといてゆく・・・。ならば、山口昌男から、本ではなく、スケッチブックが奪われたら、どうなるのか・・・。
それは悪い冗談で、山口先生のドローイング展を丸善でやったときにもしゃべったことですが、結局先生は本の活字からも、風景の線を見ているんですね。『エイゼンシュタインによるメキシコ』という本--たしか山口先生にも一冊プレゼントした記憶があるのですが--あれをみると、そういう知的な感受性のタイプというのがこの世界にはやはり確実に存在するわけです。
山口 そうしたエイゼンシュタインの世界とかモノのとら方の感覚につなげてくれるのは、今福君ぐらいでね。
今福 『踊る大地球』という先生の素描集が出ていますけれど、あの見せ方だとまだ人類学者が手遊びで描いたフィールドスケッチという文脈を超えることができません。山口人類学の思想が表面化する一手段として先生のデッサンをとらえる視角がこれから必要ですね。一方でテクストのイデアがあり、他方でデッサンがある、活字があり素描がある、というふうに並列してみて、文章と図像の本質的な対応性、緊張関係から先生のドローイング集をもう一度編集すると言うことを誰かがやってもいいかもしれませんね。
山口 今日は都市空間におけるリバーサイドの開放性を実感させるこの大変に気持ちいい風が流れるギャラリーで対談をしてきたけれども、明治大正のアーティストらの集いというのがまさにこういう空気のなかで行われるものであった。そしてアートとか演劇的な空気のなかに本が置かれる空間としては、やはりロンドンのテムズ川沿いの界隈がそういうトポスなんですね。
今福 言うまでもなく、それは西欧に限ってもイギリスのロンドンに特権化されることではなく、パリのセーヌ河畔、それこそ山口人類学にとってひとつのはじまりのトポスでもあるオデオン通りがありますし、本と水との親和性という問題があるのかもしれない。さきほど、「書物の敵」の話で水という項目がありましたが、たしかに雨で本を濡らしてしまうことがぼくも時々あって、それが洋書のペーパーバックなんかだともう二倍ぐらいに膨らみきってしまう。ところが寿岳文章は同時に面白いことを書いていて、和紙の本は、火だけでなく水にも強い、というのですね。江戸時代には近所で火事が発生すると、本を大急ぎで井戸に投げ込んだそうです。鎮火するのを待ってから、井戸からとりだして乾かせば、見事に元どおりになったとか。水は敵どころか、本を守った。
さて、やや懐古的な話になってしまうのですが、ここに『本の神話学』の単行本があります。ぼくは山口先生との1978年春の最初の出会いのとき、先生からこの本を贈られました。そういう特別な一冊なんです。もちろん実際にお会いする前から『本の神話学』は夢中になって読んでいたのですが、この本とほぼ同時期の『歴史・祝祭・神話』がぼくにとっての学問のはじまりだったといってもいいでしょう。一冊の本が無限の本に増殖してゆく迷路に自覚的にさまよい込んで、そこで言及されたり引用されたりしている文献を原典にまでたどって、そこからさらに可能な限りの文献に枝分かれしていき、無辺際の書物の森に迷い込んでゆく、そういうことをはじめてしたのが『本の神話学』を通じてのことでした。ただその当時は、というよりもそれからしばらくずっと、ぼくは不思議なことに「本とは何か」という本質的な問いをまるで考えてこなかった。それが最近、本を可能な限りつぎつぎと読んでいくことではなくて、本を媒介にした世界との裸の交渉、ということにますます関心を抱くようになっているのです。
そして同時に、本との決別、という問題も考えています。一冊も本のない世界を想像する、これは未来に実現するかもしれませんが、少なくとも現段階ではそれは一種の思考実験ですね。大学の書物論の授業でも話していることなのですが、ボルヘスは、1955年にアルゼンチン国立図書館の館長に就任して、同時にこの頃から失明する。かれの目は光りを失いはじめます。本を読めなくなるときに、膨大な蔵書の主人となるというのも凄まじい逆説ですが、しかし、ボルヘスが一連の非常に興味深い書物論を深化させるのは、じつは本を読めなくなったあとのことなのですね。ぼくの眼もすでにルビに書かれた小さな活字のパとバの区別はつきませんが(笑)、ある意味でこれは誰にでも訪れる視力の衰えという真実を暗示すると同時にそれを越えた、山口先生がしばしばいわれる文化の盲目性の問題でもある。
ふさ子夫人 じつはね、お父さんもまったくおなじで、このあいだ白内障の手術をしたときのことなんだけど、手術の直前までこうやってじーっと古書目録のちいさな字をみていて、本当にみえてるのかしらって思うじゃない。検査をするとやっぱり視力が全然ない。それでもこっちが老眼で見えない文字なんか、お父さんが本を横取りして読むと、どういうことが書いてあるか、ちゃんと言えるんだから不思議よね。だから、お医者さんが活字だけに焦点が合う目があるんだから、手術する必要はありませんよって(笑)。
今福 うーん、面白いですね。書物の活字だけに焦点が合う目っていうのが。まさに山口昌男の身体というのはそういうふうにはじめからつくられているわけですね(注:山口先生、さきほどから寿岳文章の本から片時も目を離さなくなっている)。そこでは、こういうふうに、書物そのものも肉体化している。だからこそ、逆に言えば、本のイデアというものが、山口昌男の身体を突き動かしてきた秘密の仕掛けであったことを、われわれはふかく納得するわけです。
それから最後に一言と言うとすれば、山口先生にとっての本とは、先生自身が冒頭で語られたようにはじめから本であって本でない、つまりカリグラフィーとか壁画とか絵とかマンガ、それから「背後にイメージの風景を想像させる建物としての本」--これは色々とこちらのイマジネーションを刺戟する非常に深遠な表現ですが、そういうものでもあった。ここに先日奄美でぼくが撮影してきた、二重露光の写真があります。奄美大島の芦花部という集落の古いキリスト教会に、忘れられたように置き去りにされた真っ赤な表紙のラテン語祈祷書--1920年代にドイツで印刷されたものですが、それと東シナ海に面する国直という集落のアダンの林から望む落日の風景が、偶然の力を借りてみごとに重なりました。説教台に置かれた祈祷書というのは、非常に大きくて重い。だから聖書のように聖職者の個人が持ち歩いて所有するものではなくて、すでに教会の建物の一部ですね。だからこそ、ポーランドからやってきた神父はこれを芦花部の教会に置いていった。そして建造物の一部と化したこの祈祷書を通じて、太陽が沈む多島海という永遠性の風景を、われわれは垣間みている・・・。われわれの書物論にとってある予兆の光景を映し出すこの二重露光の写真ですが、そこに託された偶然のメッセージに隠された意味を、今日もまた山口先生をつうじて学ぶことができた、そんな気がします。
(2007年5月26日、於ギャラリー・マキ。聞き書き:浅野卓夫)
●山口昌男『本の神話学』中央公論社、1971。
○山口昌男『歴史・祝祭・神話』中央公論社、1974。
○山口昌男『踊る大地球』晶文社、1999。
○Blaise Cendrars. Anthologie negre. Paris: Au Sans Pareil, 1927.
○Claude Levi-Strauss. Tristes Tropiques. Paris: Plon, 1955.
○寿岳文章『書物の世界』朝日新聞社、1949。
○Inga Karetnikova.Mexico acording to Eisenstein. Albuquerque: Univ. of New MexicoPress, 1991.
|
|
|