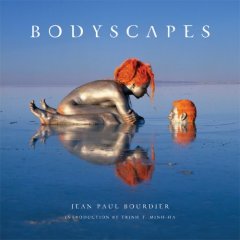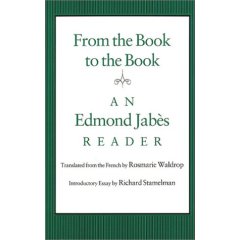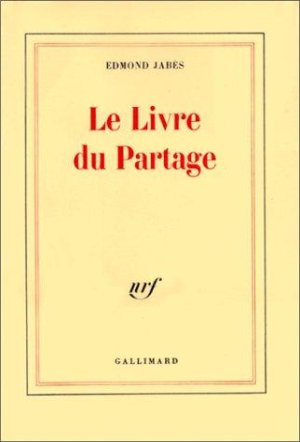「身体としての書物」
第1回
アルドゥスに倣びてー八折り本を作る
第2回
ボルヘス「砂の本」を読む
第3回
ボルヘス「バベルの図書館」を読む
第4回
ボルヘスと焚書について
特別篇
川べりの本小屋で ー山口昌男氏との対話
第5回
「ボルヘス・オラル」を読む
第6回
ジャベス「書物への回帰」を読む
第7回
ジャベス「問いの書」を読む
第8回
ページネーション考 1
第9回
ページネーション考 2
|
|
「身体としての書物」 今福龍太
第6回 ジャベス「書物への回帰」を読む
砂漠=Desertというのは、どこかで人間の本質的な思考と感覚の渇きを引き寄せる特別な地勢である、とこれまでずっと考えてきました。ぼくがもっともよく知る砂漠は、二十代の後半を過ごしたメキシコ北西部のソノラ砂漠とそれに接続するチワワ砂漠です。ソノラ砂漠は、メキシコ側から合衆国の南西部(サウスウェスト)へと国境をまたいでつながっていますが、国境などといった人間がつくりだした擬制的な近代制度の意味論を失効させる野性のテリトリーの連続体そのものです。ソノラ砂漠からさらに南へ伸びたチワワ砂漠一帯に居住するインディオ・ウィチョル族、そしてさらにその西側の半砂漠状の山岳地帯に居住するインディオであるコーラ族のもとをたずね、かれらから砂漠でくらす人間の知恵──それこそ砂漠のどこから水や食糧を手に入れるかという日常の実践から、かれらにとって砂漠という場が持つ神話的・宇宙論的な意味までを学びながら、そこが決して不毛の地ではないこと、砂漠の一見均質な風景のなかに無数の聖なる襞がかくされていることを自分自身で確認していったわけです。雨の降らない乾燥した不毛の土地、という砂漠のイメージは瓦解し、むしろ人間の思考や感覚が抱く知ることへの渇きを、砂漠がひきよせているというまぎれもない事実に気づきました。
先週まで沖縄での旅をともにし、隅田川沿いの本小屋でも対話をつづけた映像作家のトリン・ミンハは、近年、建築家である夫のジャン=ポール・ブールディエとともに "The Desert is Watching" をはじめとする、ユタ州の砂漠を舞台にした映像インスタレーションを制作していますが、今回、砂漠と身体への映像的省察である彼らの新刊『Bodyscapes』(EarthAware, 2007) をぼくに贈ってくれて、その献辞にミンハがこう書いてくれました。
For our mutual fascination for the desert and the sea
For the infinite thirst we share
「砂漠と海への魅惑」とは、これまで十数年にわたって折に触れて彼女と語りつづけてきた、事物や場所を媒介とした具体の思想にたいしてぼくたちが魅了されていることを奄美での記憶も含めて語っているのですが、その次の行にある「永遠の渇き」infinite thirstというフレーズは刺戟的で謎めいたことばの響きを宿しています。知への渇き、世界を知ろうとする渇き、というとどまることのない好奇心のことを彼女は言おうとしたのでしょうが、それが砂漠をめぐる書物の献辞として書かれたことは偶然とは思われません。水のない砂漠において人間は渇きをおぼえるのですから、わざわざ砂漠に行って渇きをいやすというのは本来はおかしい。ですがさきほどいったように、砂漠というのは、やはり人間の知の渇きを無言のまま引き寄せ、渇いた砂が無尽蔵に水を吸収するようにして人間の精神と肉体を自らの内部に浸透させてゆく、そうした究極にして最後の場であると言えるだろうと思います。
きょう、これから読むエドモン・ジャベスの知的渇望としての書物への問いかけのかたわらにも、つねに砂漠があり、砂がありました。ジャベスの作品はどれもほとんど通常の詩作品の一篇=ピースとしての完結性がみられません。だからそれはまさに砂漠のような可変的な様態をした作品であり、詩でもあり散文でもありアフォリズムであり注釈でもあるようなもろもろのテクストのかけらをかき集めたかのような、かれの書物そのものがもつ揺らぎをはらんだ流動的なかたちを暗示するものです。そしてジャベスによる砂漠でもある書物への問いかけは、つねに非常に突きつめられた、本質的で究極的な詩的言語の営みから発せられる。ジャベスの詩的な主題は、人間の感情生活とか恋愛などといった日常性とはほとんど無縁です。それに比べれば、あのボルヘスの書物論的な寓話が、充分に日常的なものに見えてしまうほどです。すくなくともボルヘスの作品には、われわれのよく知る「本」の物質的な存在感がみとめられ、われわれが感知しうる本の肉体性がまだ残されてあった。ところがジャベスの作品には、それがまったくない。観念の書物へとむかうジャベスの知のアプローチは非常に厳しいもので、謎めいたものでもあり、われわれはその道行きの周囲をそれこそ一生かけてぐるぐると逡巡しながら、砂漠としての書物の謎にすこしずつ螺旋的に近づいてゆくしかありません・・・
まず、文字通り「砂漠」"The Desert" という詩を英訳で読んでみましょうか。これは、英語で出ているエドモン・ジャベスのリーダーに収録された作品で、みじかいアフォリズムのゆるやかなつながりによって、砂漠が誘発する思想をみごとに表現しつくしています。ところでこのリーダーというのは、日本の出版文化が決定的に欠落させている書籍の形態ですね。本の意味や可能性を個別の著作に限定しないで、作家のトータリティを一冊で集約的に提示して、しかも主要テクストを絶版にさせないでつねに読者が簡単に手に取ることができる状態にしておくことは、書物を享受する愛情と配慮のもっとも基本的な条件です。では、作品をみていきましょう。
"The word of our origin is a word of the desert, O desert of our words," wrote Reb Aslan.
「『われわれの起源のことばは砂漠のことばである、おお、われわれのことばの砂漠よ』、レブ・アスランは書いた。」
砂漠と書くこと、つまりエクリチュールとが等式で結ばれている。起源は砂漠であり、砂漠はことばでもある。ここにはジャベス作品の非常に大きな特徴である概念の入れ換え、変身、波のうねりのような思考の痕跡があります。
"There is no place for the man whose steps head toward his place of birth;
"as if being born meant only walking toward your birth.
"My future, my origin," he said.
「『生まれた土地へと歩みを進める人間にとって場所というものはない、/『まるで生まれるということは、ただきみの誕生へと歩むことだけを意味するかのようだ。/『わたしの未来は、わたしの起源』、かれは言った。』
「起源」とか「生まれ」は、直線的な時間軸上の始点ではない。それは、未来でもありうる、ということは、ここで意識されているのが永遠回帰する円環的な時間だということを示しています。そして起源へと回帰する者の生涯の周囲には物理的な空間が拓けることはない。永遠と瞬時が重なるような場においては、三次元的なディメンションを持った現世的トポロジーの外部にある場が想定されねばならないのでしょう。
"There is no possible return if you have gone deep into the desert. Come from elsewhere, the elsewhere is your twin horizon.
"Sand, the asking. Sand, the reply. Our desert has no limits," wrote Reb Semama.
「『きみが砂漠の内奥へと入り込んだとしたら、帰還はあり得ない。ここではないどこかからやってくる、そのどこかとは、きみのなかにある分身としての地平線だ。/『砂、と問いかけ。砂、と答える。われわれの砂漠に限界はない』、レブ・セママは書いた。』
ここに、"your twin horizon" という詩的な表現がありますね・・・。きみのなかにあるもうひとつの地平線、双子の分身としての地平線とは、どういうことでしょう。人間にとっての場所が、そこから生を展開してゆく地平に枠づけられているとしたら、砂漠に入ることによって、そうした生きられる場所の輪郭である地平は一度消滅する。砂漠において、ひとは第二、第三の生のありかたを問うことになり、無数の地平線の分身に出会うことになるだろう。だからそこでは、ここではないどこからやってきたのかという起源への問いかけと、ここではないどこへ行こうとしているのかという未来の地平への問いかけとがひとつに結ばれる。さきほど永遠回帰、といいましたが、回帰は帰還ではありません。帰還は、直線上の始点と終点を往復する運動のことをさし、たとえ道に迷っても来た道をもどればいいのですが、砂漠では現実的にも風に吹き消されて足跡が残らないわけですから、そういう意味でも来た道をもどることはもう出来ないわけです。
「砂、と問いかけ。砂、と答える」というのも、深遠な表現で、砂漠とは、単純に不毛の地などと呼べない豊饒な響きあいの関係性のようなものだということがわかります。ある意味でこの問答は、砂のさきにまた砂があらわれる「出口なし」の状況をさすようにも見えるのですが、それにつづけて「限界はない」ということばもありますね。
A→B
C→D
通常、このように完結し安定した命題の構造が無数につらなっていくことが、論理的な思考の完全性をささえているわけですね。ところが、
S⇔S
こうなると、因果関係の構造は解体され、論理的な思考の限界がほどかれ、輪郭が砂のように崩落するわけです。しかも、
He held a bit of sand in each hand: "On the one hand, questions, on the other, answers. Same weight of dust," he also said.
「かれは両の手にわずかな砂を握った。『いっぽうの手には、問いかけを、もういっぽうの手には、答えを。おなじ重さの塵』、かれはこうも言った。」
とあって、問いでもあり答えでもある砂は塵芥にすぎない、すなわち問いへの欲望も答えへの期待も、結局は幻想にすぎないとも言っているように聞こえます。つづけて、
To create means to make the future the past of all your actions.
「創造することは、未来を、過去における君のすべての行いに変えることを意味する。」
ここでもまた、過去の未来への回帰、直線的時間の反転の関係が述べられていますね。
「模範的な規則正しさをもってユダヤ人は砂漠への出立を、かれの起源となった更新された世界におもむくことを選びとる。/創造の最中にあって、きみは起源をうみだし、それに呑み込まれる」、レブ・サヌアは書いた。/起源とは一つの深淵である。/レブ・ベヒト」
最後に「起源」ということばがくりかえされていますが、そこはもはや母胎的なユートピアではない、畏怖すべき底なしの深みであることはあきらかです・・・。ではひきつづきここからは、日本語版のテクスト「書物への回帰」のほうをみてみましょう。26ページを開いて下さい。
「世界は名前のなかへ亡命する。内部には世界の書物がある。」
この一文もまた、世界へと収斂する書物というマラルメによる本の普遍性をめぐる哲学的ヴィジョンを直ちに想起させますが、マラルメの書物論と決定的に異なる点は、ジャベスのテクストに刻印された肉体の条件、つまりユダヤ人性や亡命の問題です。ここでもまた、"TheDesert" においてそうだったように、書くこととエクリチュールが、「起源」、「底(あるいは根、英訳では roots となっています)」、「始まり」・・・と幾重にも言い換えられていることに気づきます。そういえば、ボルヘスもまた本を時間的な枠組みのなかに、つまり始まりがあって終わりがある時間、また始まりも終わりもない永遠性の無時間に置いていた、という意味ではかれも書物論的なユダヤ思考の持ち主であったと言えるかもしれませんね。さて27ページに、その「砂漠」が出てきます。
「私はある午後の終わりを思い出す。私は砂漠にひとりでいて、影が一本の針を使って空間に星をちりばめるのを見た。」
「影が一本の針を使って空間に星をちりばめる」というのは、じつに喚起的な表現ですよね・・・。「午後の終わり」というのですからまだ夜の闇が迫っているわけではない砂漠の夕空に、季節の明星が瞬きはじめたのでしょうか。おそらくその明星の光りの瞬きが天蓋の空間に無限へと通じる穴をぽつりぽつりとあけてゆく、ということでしょう・・・。いずれにせよ、これは砂漠の自然がジャベスに目撃させたひとつの特異な現象で、限界のない圧倒的な物質界にあって、光とか闇とか熱とか水への感覚があざやかに更新される様子がこのあたりの記述に比喩的に響いています。すこし駆け足で進んで31ページにいってみましょうか。ここには、「エクリチュール」ということばがみえます。
「だから私の生は、書物から見ると、諸限界の距りのなかで、発音できない『名前』の燦然と輝く徴の下で、エクリチュールの通夜となってしまうだろう。閉じ込められた昼と夜の徹宵。世界は世界の知らない間に変容する。このながい横断は眠りに混じってしまうのだ。/反復とは、人間の保持する力、神をめぐる至上の思索のなかで永遠に生き続ける力である。」
そう、「反復」とありますね。ジャベスにとってのエクリチュールとは、すなわちトーラーやタルムードなどのユダヤ教典を永遠に反復することを意味します。この点は、あとでまた触れましょう。こうした感覚は、"Magister dixit"、つまり師のことばを引き取って創造的に受け継ぐことに「書く=語る」の本質をみたボルヘスの思想にも通じます。
さて、ジャック・デリダの主著である『エクリチュールと差異』に「エドモン・ジャベスと本の問題」という文章が収録されています。アルジェリアの砂漠の縁に生を受けたもうひとりの本質的な思想家による、先人ジャベス発見をめぐるエッセイです。デリダのエクリチュール論を簡潔に要約してみると、書くことは語ることと等式で結ばれ、すべての「書く=語る」にはそれに先立って根源的な書き込み、inscription=記入がなされている。この原エクリチュールである書き込み、すなわち他者の言語を永遠に反復するようにして、われわれはなにごとかを書いたり語ったりする、そういうことですね。言い換えれば、エクリチュールは無から創造されるのではなく、言語の位置に事後的なズレをつくることであり、つまり文学とはこのズレの書き込みのことである。デリダはそれを、「differance=差延」という造語で呼びます。difference=違い/差異ということばはみなさん知っていると思いますが、フランス語の動詞differerにはもうひとつ、「遅延させる」という意味もあるんですね。このdiffererの語感と意味を残して名詞化したのがdifferance=差延という造語だったわけですが、デリダによれば、ジャベスの詩こそこの反復と書き込みによる差延的文学表現の至高のケースだ、というわけです。
エドモン・ジャベスの履歴についても、簡単に触れておきましょう。ジャベスは1912年にカイロのユダヤ人家庭に生まれ、フランス語で教育を受けて、1991年に亡命先のパリで没しています。エジプトのカイロというのは歴史的にみて地中海世界の宗教や文化の交差点のひとつでした。中世から近世にかけて離散ユダヤ人が集中した都市で、エジプトだとアレクサンドリアもそういう場所です。カイロには、エドワード・サイードのようなイスラエルの建国によって離散を強いられたパレスチナ人ものちに流れ込んできました。ですから、ジャベスとサイードは、大変に短い時間ではありますが、1950年あたりにおなじ都市でおなじ時間の空気を共有していたことになります。さて1954年、エジプトでクーデターが勃発して、ナセルが政権を樹立します。ナセルという軍人政治家は、59年にキューバ革命をおこしたカストロらと並んで、60年代の非同盟主義系指導者のシンボル的な存在だったわけですが、かれが唱導する汎アラブ民族主義、つまり反ユダヤ、反イスラエルのキャンペーンによって、ジャベスは追放されるようにしてフランスに亡命します。そしてパリで詩人として自己形成を遂げ、非常に影響力ある作品をフランス語の文学界にいくつも残したのですが、いかなる文壇にもグループにも出入りせず、文学者としては孤高をつらぬいたようです。
ジャベスによる書くことの本質をめぐる書物論的な問いかけを、ふたたびいくつかのキーワードとして抽出してみると、たとえばこうなるでしょう。
・ 砂漠=砂
・ 書物
・ ユダヤ性
・ エクリチュール
・ 井戸
最後の「井戸」というのは、最近のぼくやトリン・ミンハの想像力をもひきつける特別なトポスですが、このなかでとりわけ「砂漠」、「書物」、「ユダヤ性」は、これまで何度もくり返し指摘してきたように、ジャベスにとって同一現象の入れ換えとして絶えず意識されています。ジャベスのテクストにあって、書物は本という物理的な実体にとどまらない何ものかをさし、しかも本をめぐる話題が何の前触れもなく砂漠をめぐる話題にすりかわり、またそれがいつのまにかユダヤ人の身体性をめぐる話題になっている、ということはしばしば起こります。ボルヘスの場合メタファーとしての本は有と無のあいだで、巨大化と極小化とのあいだで膨らんだり縮んだりするわけですが、ジャベスの場合には本が本でないものにあっさりと変化する。書物論的な奇術師にはこの二つのタイプが存在すると言えそうですが、こうしたマジックゆえにジャベスのいう書物が一体何なのか、われわれにはなかなか分からないわけです。ともかく、ユダヤ人の遍在性を運命づけたディアスポラ、つまり歴史的な流謫と離散、より近代的な用語でいえば亡命とは、かれらが砂のような断片として世界へ散種される経験であり、それがジャベスにとっては書物のありようそのものでした。書物だけが、エクリチュールだけが、したがって世界へあまねく撒かれた砂粒のようなユダヤ人の住処である、そういう感覚ですね。ジャベスの1959年刊の処女作のタイトルは、『私は私の住まいを建てる』Je batis ma Demeureというものでした。ここで「住まい」と訳されているのは、フランス語原文では demeure、英語ではdwellingとなっていますが、これは、本源的な「家」というよりは、ある場所にとどまることによってそこが住み処となる、という多分に過渡的・一時的な居所を意味しています。つまりここでいう「住まい」がhomeではないということがひじょうに重要で、abroad(よそ)に対立するhome(ここ=家郷)が定住的なアイデンティティを支える場だとしたら、dwellingとはその時その時の仮設的な住処をさし、しかも移動の中の居住をめぐる歴史的・集合的経験を意味します。
では、ジャベスにとってそこに住まう本とはいったい何ものだったのか? この問いかけの「本」という部分を、とりあえずエクリチュールと言い換えてみると、かれにとってエクリチュールとは、さきほど指摘したように、ただ単に自分の言葉で書くことだけではなく、誰か他者の言葉のおとずれを待つこと、つまりタルムードというユダヤ教典の口伝書におけるラビ(師)の言葉を引用し、そこに「上書き」することでもありました。ジャベスの書物論的思想に深い影をおとしているユダヤ教典の二重性、リテラシーとオラリティの問題についても、このあたりで確認しておきましょう。現在のユダヤ教典には、大きく分けて『トーラー』と『タルムード』の二種類があります。『トーラー』のほうは、いわゆるモーゼ五書、つまり創世記、出エジプト記、レヴィ記、民数記、申命記のことで、書かれたテクスト、まさにエクリチュールです。古代イスラエル最大の預言者モーゼによって「書かれた」と伝えられている教典(テクスト)が『トーラー』なのであり、それが文字として固定化されていることが重要です。一方、『タルムード』のほうは、日本語では口伝律法などと訳されますが、オーラルな伝承で、つまりパロールの側に属している。「タルムード」というヘブライ語は、もともと「研究」という意味で、モーゼ五書の研究・注釈を口伝したものを、およそ2世紀頃のローマの帝国権力に対するユダヤ人の最後の闘い、ユダヤ教の消滅の危機のさなかにラビたちが文字化して書物として編纂したもので、後にこの口伝書そのものがタルムードと呼ばれるようになりました。これらもたしかに最終的には「書かれた」テクストとなって残されましたが、あくまで口伝律法だったものをラビたちが聴き取って保存のためにテクスト化したものであり、いまだ口承的なゆらぎがそこに孕まれている。ジャベスの詩には無数のラビRabh=Reb たちの言葉の引用としてのテクストが引かれていますが、これがジャベスにおける「書き込み」の原基ということになります。いずれにしても、ユダヤ経典におけるエクリチュールと口承性の二重性の問題が、ジャベスの思考、とりわけ彼の耳と手の関わりをめぐる思想をつねに刺戟しつづけているのです。
エドモン・ジャベスのテクストを読むとき、こうしたユダヤ性やユダヤ教典の文脈への言及を抜きにすることは難しいのですが、しかしそこには異教徒には決して踏み込めない宗教的完結性・閉鎖性はない、ということもまた事実です。われわれの「身体としての書物」という拓かれた主題にとって、とりつくシマがまったくない、というわけではない。たとえば、亡命という身ぶりは、ジャベスをふくむユダヤ人の近代的生存のリアリティを映し出す様態ですが、そこにはつねにExodus、つまり出エジプトという起源からの離脱の物語へと回帰する時のパサージュがかくされている。現代の亡命の境涯に、出エジプトという原初の移動があらかじめ書き込まれている。そしてデリダ的な意味でのこの根源的な記入こそが、まちがいなくジャベスのユダヤ思想と生の軸、詩を書くという行為の軸をなしているはずです・・・。
さて、もう時間が来てしまったので、きょうはとりあえずここまでにして、次回もまたひきつづきジャベスの書物論的テクストを読み継いでいきましょう。
(2007年6月19日、於東京外国語大学「表象文化論演習」。聞き書き:浅野卓夫)
●Edmond Jabes. "The Desert", From the Book to the Book: An Edmond Jabes Reader.Wesleyan University Press, 1991.
○エドモン・ジャベス『書物への回帰』鈴木創士訳、水声社、1995。
○ジャック・デリダ「エドモン・ジャベスと本の問題」『エクリチュールと差異 下』阪上脩訳、法政大学出版局、1977。
|
|
|