「身体としての書物」 今福龍太
第3回 ボルヘス「バベルの図書館」を読む
今日は、ボルヘスの「バベルの図書館」を読みます。ボルヘスは、つねにあるひとつの巨大で根源的なテーマを手法を変えて変奏してきた作家である、といえるかもしれません。それは世界であり、無であり、永遠であるような何かです。そしてこのテーマは、この講義での文脈に即して言えば、書物という形態をとってこの世にあらわれることもある、そういうことですね。ともかく、先週の「砂の本」から、今回の「バベルの図書館」へとテクストを読み継いできて、そこには書物という共通のモティーフがあるわけですが、この二つの作品からは、ずいぶん異なる印象を受けたと思います。前作の主人公というか舞台が一冊の本であったのに対して、今回は本のある空間、というように、ボルヘスによる書物論的な主題へのアプローチや物語上の技巧の移行が、ここにはあきらかに存在します。
さて、本格的な読解に入る前に、すこし寄り道をしましょうか。じつは先週末まで、奄美大島に行ってきました。次回の奄美自由大学のためのロケーションハンティング、というのが一応の目的だったのですが、今回は--というか今回もというべきでしょうか、じつに刺戟的な発見にみちた旅になりました。島の集落や自然の地勢を舞台に巡礼する、ということで、奄美大島を回りながら、これまで島の土地と自分とが共鳴してあってきた時間、過去の記憶のディテールを探りながら、今群島の無意識が何をやりたがっているか、そういう感触をたしかめていたわけです。そして、道行きの途中で、すばらしい本との出会いがありました。それは、アシケブ=芦花部という、奄美大島北部・龍郷町のおよそ30戸の小さな集落でのことでした。
奄美には、古く日本群島一帯で信仰されていた自然宗教の空気がいまなお色濃く残っています。それは、本土などでは、神道や仏教が中世以降に国家宗教として制度化され、神社や寺が建造される動きの中で、抑圧されていったものですね。奄美・沖縄の聖地とは、何もない空間です。岩室とか海岸が聖地である例もありますが、基本的には森や山の空地です。芦花部集落には、神山(カミヤマ)、もしくは照山(テラヤマ)--これは、言うまでもなく後代の当て字ですね。テラ、というのは島の言葉で太陽のこと。つまり、テラ山というのは、太陽崇拝の場で、それが照らすの「照」、あるいは寺社の「寺」になっていったわけですーーのかたわらに、神社があります。これは奄美群島の集落によく見られる宗教的な景観ですが、結局は、近世以降国家神道が周縁の島のかつての聖地を征服していった暴力性のしるしですね。そしてこういう場合、神社は、かならず聖地の「場所の軸」と垂直に交わるように建てられている。ここで鳥居は、東西の軸に沿ってたっているのですが、本来の神山の軸は南北だったと思います。ともかく、そうした背後に山をひかえる集落の聖なる空間の隅に、芦花部教会はひっそりと佇んでいました。
芦花部教会には、不思議なことに、島の聖地を征服し調伏しようという暴力性、たとえば中南米の植民地のカトリック教会にみられる、布教と征服が表裏一体になった歴史の暴力性の痕跡が、ほとんど感じられないのです。どちらかというと、聖地の自然と共存しようとしているようにも見える。もともと日本の南西部で持続的に布教されてきたカトリックは、長崎の例にも見られるように、周縁の少数者や貧困がかかえる諸問題をその最底辺において受けとめる、そういう真摯な熱情、伝統がありますね。ともかく、その教会は、昭和5年に建てられた古い木造教会で、また空間の内部がすばらしい。木の柱や梁、床など、随所に工芸的で、有機的・身体的な美しさをたたえていました。そこで司祭の古道具などを色々夢中になってひっくり返していたりしたのですが、一冊の、赤い表紙のラテン語祈祷書がみつかって、それはミサの祈祷文とかオラトリオの楽譜などがおさめられているものです。1920年にドイツで印刷された、とありましたから、それこそグーテンベルグ以後、20世紀に至るまで、聖書印刷出版のひな形がここドイツにあったということになります。この聖典を説教台のシーツの上にそっと置いて、ひもといてみる、そうした無時間のような時間をしばらく教会ですごしました。
奄美では、「ヴァイタル」とわれわれが呼んでいる、二重露光写真もとってきました。一枚、おもしろい写真をみせましょうか。露出を半分ぐらいに落として、一本のフィルムで二重撮りをするという仕掛けですね。一回めのフィルムの何コマめに何を撮影したかなんていちいち覚えていないので、これは完全に偶然性の産物です。すると、大和村国直のアダンの林越しの海に沈む夕日と、この聖典・祈祷書のイメージが、見事に重なったわけです。まるで「砂の本」を思わせる、永遠としての書物の像が、ここに浮上しました。なにか、暗号としての写真が、ここにあるようですね。
 (c)Ryuta Imafuku (c)Ryuta Imafuku
前置きが長くなりましたが、大急ぎで本題に戻りましょう。先週のテクストに描かれていた「砂の本」ですが、あれは、本としての手触りや質感、物質感をみなさん何となくイメージできたとおもいます。ところが、「バベルの図書館」となると、なかなか空間をイメージすることができないのではないでしょうか。ぼく自身も、これまで何度も試してみたのですが、どうしても設計図が書けない。冒頭から、小説は空間構造のディテールを実に克明に、具体的に描写しているようでいて、「バベルの図書館」というのはやはり不定形、不透明な空間なのです。
「その宇宙(他の者たちがいうところの図書館)は、真ん中に大きな換気孔があり、きわめて低い手すりで囲まれた不定数の、おそらく無限数の六角形の回廊でなり立っている。どの六角形からも、それこそ際限なく、上の階と下の階が眺められる。回廊の配置は変化がない。一辺につき本棚が五段で、計二十段。それが二辺をのぞいたすべてを埋めている。高さは各階のそれであり、通常の図書館のものをわずかに超えている。棚のない辺のひとつが狭いホールに通じ、このホールは最初の回廊やすべての回廊に通じている。ホールの左右にふたつの小部屋がある。ひとつは立って眠るため、もうひとつは排泄のためのものである」
ここでいう「六角形」というのは、ボルヘスにとって、永遠の循環性、対称性のシンボルですね。ところで、翻訳テクストの冒頭の一文に、ぼくは大変な不満を感じます。いつもここで、つまずくんですね。「その宇宙(他の者たちがいうところの図書館)は」、まあ、ここまではいいでしょう。問題は次、「真ん中に大きな換気孔があり」となっていますが、「バベルの図書館」にとって重要なのは、「換気孔」ではやはりない。日本語訳では1「換気孔」、2「きわめて低い手すり」、3「不定数の、おそらく無限数の六角形の回廊」の順になっていますが、ことばを通じて読者の頭脳にまず飛び込んで来るべきイメージは、この最後の「六角形の回廊」にほかなりません。スペイン語原文では、当然3、1、2の順になっていて、形容句を先にもって来る日本語の翻訳作法にならった文とは言え、これではやはり、ボルヘス的物語の基本的手続きを、訳者は完全に無視していると言わざるを得ません。
さて、書棚の配置の説明の仕方には、何カ所かで矛盾があるようにも思えますし、77ページでは、「いくつかの公理をおもいだしておきたい」と述べながら、第二の公理で途切れたまま物語がそのまま進行してゆきます。学術論文とはちがいますから、論理的な整合性がなくても、まあおかしくはありませんし、これが読者を軽い錯乱へと導くボルヘス的な仕掛けだ、と言えるのかもしれません。
「バベルの図書館」というこの作品を読んでいると、迷宮構造の中に幽閉されるような閉塞感、これはたしかに感じますね。ところが読み進めるうちに、ひとつの疑問が生じます。「バベルの図書館」にははたして「外部」が存在するのか、というのがそれです。言うまでもなく、そこには「外部」がない、つまり、外の世界から遮断されて閉じ込められるような経験とは、あきらかに別種の経験がそこにはあるはずです。
話は少し変わりますが、ボルヘスは1899年生、20世紀がはじまる一年まえに生まれた作家ですが、これは1941年の作品です。ここで考えてみてもいいのは、ボルヘスが、1955年にアルゼンチン国立図書館の館長に就任していることです(それ以前に、もっと小さな図書館に勤務した経験は、ありました)。それで、就任にあたってこのような言葉を残しています。「自分はこれによって80万冊の書物を与えられたが、同時に暗闇をも与えられた」。これはどういうことかといいますと、この頃からボルヘスは失明する、かれの目は光りを失いはじめたということです。本を読めなくなるまさにそのときに、80万冊の本の主人となる。何と言うパラドックス、神の皮肉でしょう。後半生において、ボルヘスは、文字を読むという形では書物とつきあうことができなくなりました。しかし、ボルヘスが自己の書物論を深化させるのは、ある意味で、本を読めなくなったあとのことなのですね。本というモノが、けっして情報媒体に収斂するものではないこと、コンテンツ、などといういまや極度にやせ細ったことばや概念といかに無縁であることか、このエピソードひとつとってもよくわかります。じつは、すでに1941年に執筆された「バベルの図書館」の物語でも、失明の兆しがあったことは暗示されていましたよね。
さて、79ページに、「ある天才的な司書が図書館の基本的な法則を発見した」とあります。「ある天才的な司書」、これはボルヘスのことかもしれませんね。それはともかく、しばらくして「「広大な図書館に、おなじ本は二冊ない」彼はこの反論の余地のない前提から、図書館は全体的なもので、その書棚は二十数個のあらゆる可能な組み合わせ(その数はきわめて厖大であるが無限ではない)を、換言すれば、あらゆる言語で表現可能ないっさいをふくんでいると推論した」と書かれています。そして、「いっさいとは、未来、詳細な歴史、熾天使らの自伝、図書館の信頼すべきカタログ、何千何万もの虚偽のカタログ、これらのカタログの虚偽性の証明、真実のカタログの虚偽性の証明、バシリデスのグノーシス派の福音書、この福音書の注解、この福音書の注解の注解、あなたの死の真実の記述、それぞれの本のあらゆる言語への翻訳、それぞれの本のあらゆる本のなかへの挿入、などである」。カタログというのは、書誌の本、どの本が何所にあるのかが記載されたインデックスのことですが、この引用箇所は、虚実入り乱れた本についての本、そうしたメタ書物が無限に増殖してゆく書物の迷宮を描ききった、いかにもボルヘスらしい面白い表現ですね。「それぞれの本のあらゆる本のなかへの挿入」、とまでなると、注解の注解、コピーのコピー、引用の引用をこえて、ある一冊の本がまるごと、本としての形と物質感をそのまままもったまま、別の本に差し込まれる、そうした異形の書物のイメージすら浮かびます
つづけて、「図書館があらゆる本を所蔵していることが公表された時の最初に生まれた感情は、途方もない歓びであった。すべての人間が手つかずの秘密の宝物の持ち主になったような気がした。その有効な解決が六角形のひとつに存在しないような、個人的あるいは世界的な問題はなくなった。宇宙は根拠が与えられ、宇宙は突然、希望の無限の広がりを獲得した」。ここでいう「感情」、とは、全体性の真実をめざす人間の欲望のことでしょうね。それから、「そのころ、「弁護の書」というものが大きな話題となった。弁明と予言の書物がそれで、宇宙の人間一人ひとりの行為を永久に弁護し、その未来のために驚くべき秘密を蔵しているものであった」。この「弁護の書物」というのは、一種のユートピア、のようなもの。「何千という貪欲な人間たちが懐かしい生地(きじ、ではなく、せいち、ネイティブの土地という意味ですよ)の六角形を去り、己の弁明を発見しようという空しい意図にせき立てられて、階段を駆けあがった」。そう、すべての人間は六角形で生まれ、やがてそこを出て、階から階へとさまよう・・・。ここまでくると、これが、われわれの世界、宇宙そのもののありようだということが分かります。世界そのものが、広大無辺の空間ではなく、閉ざされた迷宮としてあるのだと言う、直感、予感がわれわれの頭脳をつらぬく瞬間です。その後の、この書物を求めてさすらう巡礼の争い、「呪詛のことばを吐いた」、「たがいの首を絞めた」、「いかさまな本を穴の底に投げた」、ひとびとの死、発狂・・・、これはもう現代世界の人間の愚行そのものだと言っていいでしょう。「「弁護の書」は存在する」。これは、「砂の本」、神そのもののような存在ですね。そして、「(未来の人間たち、おそらく想像のものではない人間たちに関する二冊を、わたしはこの目で見たのだ)」、「二冊」といっているところに注意して下さい。ところが、「しかしそれを求めるものたちは、一人の人間が己のものを、すなわち己のものの偽物を発見する可能性はゼロだということを考えようとしない」。先ほどは「存在する」、しかも二冊目撃されているといっていたのが、今度は「可能性はゼロだ」となっている。これ=これでない偽物、というのは論理学的に言えば完全な矛盾ですが、ここでボルヘスは、オリジナル/コピーの境界の破綻を宣言しているのでしょう。
サラエボ国立図書館の話をしておきたいと思います。知っている人も多いと思いますが、この図書館は、旧ユーゴのボスニア内戦の際に崩壊・炎上しました。ここは、アドリア海・バルカン半島の歴史的な都市ですが、スラブ人による定住、ハンガリー支配をへて、15世紀オスマン帝国の属国になり、イスラム教が進出してきます。そして19世紀にハプスブルク帝国に占領されて、カトリックとイスラムの確執があった。そればかりか、そこには歴史的に、ディアスポラのユダヤ教徒も多く存在してもいた。それが、ボスニア・サラエボが文化・言語・宗教の十字路と呼ばれる所以の歴史ですが、だからこそこの都市には、深い学問・知識が蓄積されることになりました。サラエボ国立図書館はムーア様式の建造物で、一説によれば、200万冊の蔵書--そのほとんどがイスラム関係の本だったということですが--を有していた。山口文庫の50倍、まあこういった場合、サラエボ国立図書館のほうが偉大なのか、山口文庫が偉大なのか、どちらを意味するのかわかりませんけどね(笑)。図書館は1992年の8月、ボスニア内戦でセルビア軍の砲撃を受けました。蔵書は完全に焼失、三日三晩、建物ではなく、本だけが燃えつづけた、と言います。サラエボの都市とそこの人間の歴史と記憶は、蔵書として実在していた、と言っていいでしょう。だからこそ、サラエボという都市の息の根を止めるためには、市庁舎でもなく軍部でもなく、国立図書館を灰にしなければならない、というのが、攻撃する側の無意識の意図だったのでしょう。都市の知的中心地を攻撃することが、征服という出来事の象徴となることは、世界の軍事行動の歴史からもあきらかです。「焚書」というのは、文明の歴史でくり返し行われてきたことです。もしかしたら「砂の本」という作品は、この「焚書」の問題を暗示していたのかもしれません。
最後に、ボルヘスの盲目性にもどりましょう。「砂の本」の書かれている文字が読めないことの意味は、謎で未知の言語の問題であると同時に、目が見えないことの比喩なのかもしれません。じょじょに訪れる視力の衰えによって、書かれている文字のディテールが、まるで砂のように崩壊してゆく・・・。盲目のボルヘスがもはや読みえない書物をもって、「焚書」について思考しているのだとしたら、それはじつにスリリングな図です。本というものが、肉体性、つまり重さや肌触りや匂いも含めて、無限を媒介する事物としてあらわれ、その無限性を思考の力によって、可能な限り遠くへと引っ張ってゆくこと、それはじつに魅力的であると同時に恐るべきすがたです。
来週は『ボルヘス、オラル』からとったテクストを読みます。「口頭で語る、ボルヘス」といった意味の講演集ですが、視覚を完全に失い、声の人、耳の人となったボルヘスのまずはじまりの講演テーマが「書物」だったというのも、じつに示唆的です。それでは、また来週。
(2007年5月15日、於東京外国語大学「表象文化論演習」。聞き書き:浅野卓夫)
●ホルヘ・ルイス・ボルヘス『伝奇集』鼓直訳、福武書店、1990(岩波文庫、1993)。
|
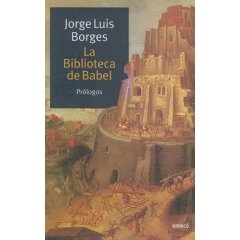


 (c)Ryuta Imafuku
(c)Ryuta Imafuku